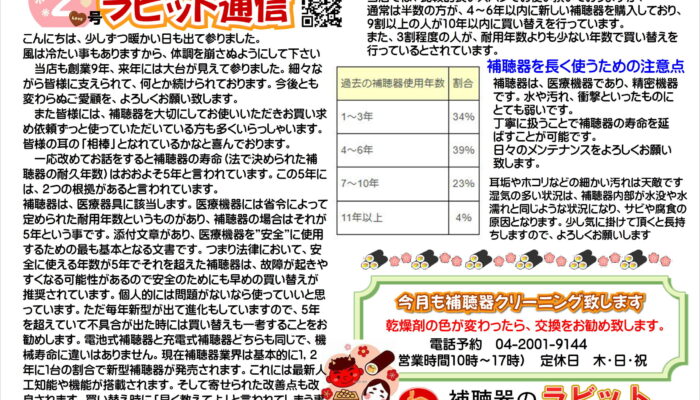ラビット通信 2025年4月号
 2025年4月号
2025年4月号
こんにちは、寒暖差に負けていないですか?
もうすぐ暖か日になります、元気を出していきましょう!
最近「言葉」に対して新たな発見をしました。私は「でも」という言葉に最近「言葉」に対して新たな発見をしました。私は「でも」という言葉に対して否定的で、出来るだけ使わないようにしていました。「でも」最近読んだ本により、意見が変わりました。
脳科学者の西剛志さんによると「何気なく発している言葉が、脳に大きな影響を与えている。言葉の使い方が悪い人は、老人脳になるリスクが高くなる」という事です。そこには脳の老化スピードが速い人がよく使う言葉があるという事なんですが、
「あー、疲れた」 「もう、嫌になる!」 「そんなことできるわけない」などの否定的な言葉は「脳のプライミング効果」で脳に影響を及ぼし、老化を進めてしまうそうです。使った言葉がその後の行動に影響を与えるということです。どういう言葉を使うかで、無意識のうちに行動が変わります。「疲れた」を多く使っていると歩くスピードが遅くなるという事が実験で結果として出てきたそうです。
そうはいってもつい口から出てしまうこともありますよね。それに、使わないように無理に我慢すると、逆にそれがストレスになってしまう人もいます。西先生の実験でも、たとえば、疲れているのに「疲れている」と言えないと、何かモヤモヤした感じになってしまう人が多数出たそうです。そこで先生が考案したのが、「『でも』の法則」です。マイナスの言葉を言ったあとに、必ず「でも」を付け加えるという方法です。
「疲れた。でも、がんばった」
「疲れた。でも、いい疲れだ」
「疲れた。でも、寝れば回復するだろう」
「疲れた。でも、その分成果が出た」
脳は、文章の一番最後にきた情報を印象に残しやすいという性質があります。なので、「疲れた」が最後であれば「疲れた」という情報を残しますし、「でも」のあとに「がんばった」と言うと「がんばった」という情報を残せばいいそうです。
人は楽観的性格と悲観的性格の2つに大きく分けられるのですが、楽観的な人はポジティブな言葉を使い、悲観的な人は自分にも人にもネガティブな言葉を使う傾向があります。ネガティブな言葉を使うと脳はストレスを感じるため、老人性うつの原因にもなり、認知症のリスクも高まってしまいますから今日から積極的に「でも」を使おうかと思っています。
「あ~肩が凝った、でも ラビット通信仕上がった!」
参照:西剛志著書『増量版 80歳でも脳が老化しない人がやっていること』(アスコム)